現実に戦争が起こったら?そんなことを想像させられる、「現代の戦争小説」を読んでみたくありませんか?今回は砂川文次さんの小説「小隊」を特集します。元自衛官の作家ならではのリアルな描写が読みどころですが、他にも意外な読み方ができる作品になっているんです!あらすじや感想、さらには芥川賞の受賞予想もまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
砂川文次のプロフィール
砂川文次さんは元自衛官の肩書きを持つ、変わり種の作家。2016年に文學界新人賞を受賞してデビューしました。デビュー作である「市街戦」は陸上自衛隊操縦学生時代に書き上げ、自らの経験を活かした作風が高く評価されました。
その後、4作目の「戦場のレビヤタン」が第164回芥川賞の候補作に。イラクの紛争地に赴任した民間警備会社勤めの青年の姿を描いた本作は、戦場のディテールがよく描かれていました。芥川賞選考会では辛口の評価が多かったですが、彼にとって一つの出世作となりました。
「小隊」は第164回芥川賞候補作に選出される
『文學界』2020年9月号に掲載された「小隊」は、第164回芥川賞の候補作に選ばれました。今回の芥川賞は、バンド・クリープハハイプの尾崎世界観さんや、弱冠21歳の宇佐見りんさんが候補となっており、そちらの方が話題先行になっています。
毎回、芥川賞候補になるのが4回目や5回目の作家が入ってくるのですが、今回は過去に候補作となったのは砂川さんと乗代雄介さんだけ(どちらも2回目)。作家歴だけでいうと、砂川さんが最も長いことになります。
記事後半では、彼が芥川賞を受賞できるか、ズバリ予想していますので、そちらもお楽しみに。
「小隊」のあらすじとは
舞台は現在の北海道釧路地方。ロシアが攻めてくるという報せを受け、配属された自衛隊の顛末を描いています。主人公は小隊長の安達という人物です。
前半では戦闘がまだ始まらず、住民も自衛隊隊員たちにも「本当に戦闘が始まるのか?」と不確かな気持ちのまま業務をこなしています。しかし後半では実際に戦闘が始まり、仲間が命を落としたり、安達が敵を殺したりと激しい描写となります。
「小隊」の読みどころ4つ
「小隊」は戦争もの小説の一種ですが、
・舞台が現代だということ
・元自衛官が書いていてリアリティーがあること
などが特徴で、いろんな読み方ができる作品です。
そこでここでは「小隊」の読みどころを簡単に解説します。
軍事マニアにおすすめの戦闘シーンのリアリティー
冒頭にも紹介したように、筆者は元自衛官という肩書きを持っています。実際に職務に就いていた者ならではのリアリティーがあり、まずはそこが最大の読みどころと言っていいでしょう。
噴煙というにはあまりにも淡い、白い靄が発射地点を覆っている。飛翔音は、タイヤとかボールから空気が漏れる音に似ていた。白い線を引きながら、ミサイルは擱座しているT-90にすっと吸い込まれていった。
引用:文學界2020年9月号78ページ
こちらはロシア軍が攻めてきた際に、最初に応戦のミサイルを放った時の記述です。映像も音も呼び起こすリアルな描写で、いよいよ戦闘が始まるのだと思わされます。
戦闘の命令を出す無線には専門用語が多く少し分かりにくいですが、ニュアンスは伝わってきます。「槓桿」などの武器の専門用語、戦闘時の隊員の配置など、軍事オタクが気に入りそうな表現がたくさん出てきます。
時間感覚や死生観を狂わせる、凄惨な戦闘シーンの描写
凄惨な戦闘シーンで、主人公は何度も自分を見失いそうになります。
どれほどの時間が経っただろうか、唐突に砲撃が始まった。複数発、あるいは数十発の同時弾着だった。文字通り地面が震え、壁や天井の土が降り注ぐ。
引用:文學界2020年9月号97ページ
時間の感覚が麻痺した状態で戦闘するシーン。
「分隊長はいるか」
「死にました」
うなじから、肩甲骨までにかけて痒みが走る。佐藤1曹か。そうか、死んだか。なんの感情も呼び起こされなかった。
引用:文學界2020年9月号95ページ
さらには仲間の死にまでも何も感じないほど、心が消耗しています。こういった心理描写も巧みです。
平凡な日常と地続きの戦場での描写や主人公の心情
物語の前半はまだ戦闘が始まる前で、主人公たちは「本当に始まるのだろうか?」とぼんやりした気持ちにさせられることが多々あります。これは前回芥川賞候補になった「戦場のレビヤタン」にも共通する点です。
戦闘が始まった時も、ラジオでは戦況を詳しく伝えず、日常的な何気ない放送を流しています。また主人公が彼女に自分の仕事のことを分かってもらえないと嘆いていたり、テレビ見ながらダラダラしたい、プレステでバイオハザードしたいと思ったりします。
一種の戦争小説でありながら、それは平凡な日常とつながっているというのが、妙にリアルな気持ちにさせられます。
上司と部下に挟まれた、中間管理職としての立ち振る舞い
「小隊」とは、軍隊における一つの階層のこと。軍隊の編制は以下のようになっています。
軍(army) – 軍団(army corps) – 師団(division) – 旅団(brigade) – 連隊(regiment) – 大隊(battalion, squadron) – 中隊(company, battery, troop) – 小隊(platoon) – 分隊(又は班)(squad) – 班(又は組)(team) – 組(fire team)
引用:Wikipedia「軍隊の編制」
主人公の安達は小隊における隊長であり、会社組織でいうといわゆる中間管理職。上からも下からもプレッシャーを感じる、地位に就いている訳です。
安達は上司から理不尽な命令を聞きつつ、部下には厳しさと優しさを持って接する、理想的な振る舞いをしています。しかも戦場という難しい現場で何度も自分を見失いそうになりながら。
自分を支えるのは不撓不屈の精神でも高邁な使命感でも崇高な愛国心でもなく、ただ一個の義務だけだった
引用:文學界2020年9月号
とあるように業務があるからこそ動く「義務感」に支えられながら安達は何とか生き延びていきます。この姿勢はもしかしたら、厳しい立場で働いている世の会社員の方々にとって何かしら教訓というか、働く上でのヒントになるかもしれません。
「小隊」の評判は?口コミ評価レビューまとめ
「小隊」のSNSでの評判をまとめました。
砂川文次『小隊』
作者の経験が遺憾なく発揮された意欲作。
戦後七十五年を経て、領海侵犯や近隣国による実力行使が報道される昨今。現実に起こりうる様々な危機を意識しつつ、戦場のリアルを描くこの作品を目にする意味を、深く自問せざるを得ない。— 瑪瑙 (@menou_main) August 16, 2020
砂川文次『小隊』北海道での対ロ地上戦。すぐ隣にあるかもしれない歴史。物凄く凄かった。あんまこんなことは思わないけど、気になってる人がいたらぜひ読んでほしい。
— Qへい (@Q_cub) December 22, 2020
ロシアとの北方領土問題はずっと解決されないまま現在に至っているので、起こり得なくもないテーマですね。実際には絶対起こってほしくないですが…。
砂川文次「小隊」(『文學界』2020年9月号)読了。専門用語と漢語多めの硬質な文体からは戦場の緊張感が伝わってきた、そこにふと紛れる俗っぽい柔らかい言葉が作品全体にリズムを与えているように思った。良い作品だった。 pic.twitter.com/OnKEUgxV3J
— atohs (@atohsaaa) December 30, 2020
全体的なバランスの良さを評価されていますね。
小隊/砂川文次#読了
形式としては、自衛官である安達の職務日記のような形を取っていて、とても固い文章なのだが、所々で組織とは、現代社会で生きるとは、といった様々な問いを投げかけてくる
日本での戦争という非現実的なものが、現代社会を写す鏡になっている#読書好きと繋がりたい— なつ@読書垢 (@natsu_dokusho) January 6, 2021
組織における役割をテーマとしてあげていますね。
「小隊」は芥川賞を受賞できる?ズバリ大予想!
「小隊」は第164回芥川賞を受賞できるか、ズバリ予想します。前回候補になった「戦場のレビヤタン」は全体的に低調でした。それに比べ、今作は戦場のリアルなシーンの描写がしっかり書かれているので、評価は高くなると思います。
ただ、その一方で戦争が始まった理由について深く書かれていないポイントはマイナス評価に繋がりそうです。戦う理由が分からずに理不尽な戦闘に巻き込まれていく、という作者の狙いかもしれませんが…。
いずれにせよ、戦争ものは選考委員が厳しめに評価する傾向にあります。「なぜ今、戦争を書く必要があるのか」という文学的意義を問い出した場合、どうしても不利になるのではないでしょうか。受賞は難しそうだと言えます。
ちなみに本サイトでは他の候補作品についても受賞予想を含めた記事を書いているので、そちらもぜひチェックしてみてください。
※尾崎世界観の「母影」の紹介記事はコチラをチェック!
※砂川文次の「小隊」の紹介記事はコチラをチェック!
まとめ:「小隊」は元自衛官ならではのリアルな描写が読みどころ!
砂川文次さんの「小隊」についてまとめました。現実にもあり得そうな舞台設定と、元自衛官ならではの場面描写が魅力の1冊。軍事マニアの方はもちろん、現在の組織での立ち振る舞いについて考えたい方にもおすすめの小説となっています。気になった方はぜひ読んでみてください。
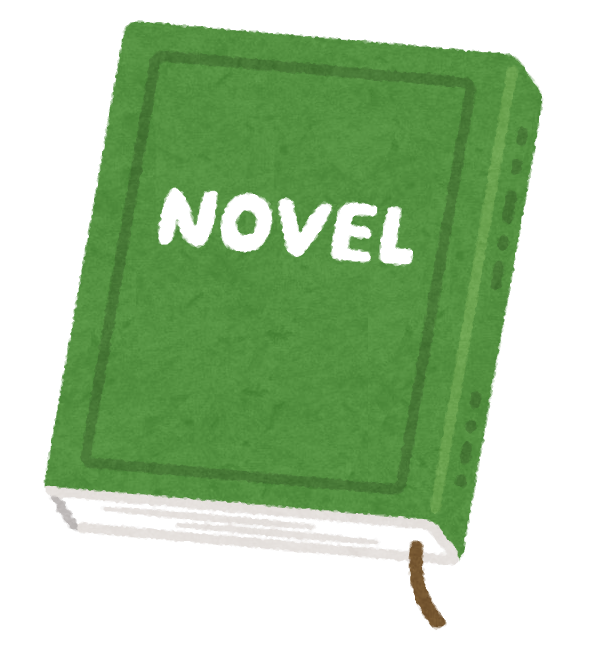


コメント
[…] ※尾崎世界観の「母影」の紹介記事はコチラをチェック! ※砂川文次の「小隊」の紹介記事はコチラをチェック! […]
[…] ⇒「小隊」についてまとめた記事を読んでみる […]