芥川賞の話題や近代文学を習う上でよく聞く、「純文学」というジャンル。しかしこの「純文学」を一言で説明してと言われると、難しいですよね。そこで今回は純文学の明確な定義や、大衆文学やエンタメとの違いを明らかにしていきます。また「難しい」や「読みにくい」とイメージされがちな純文学を楽しむ方法や、代表的な作家、そしておすすめ作品も紹介します。
純文学とは?定義や大衆文学との違いを解説
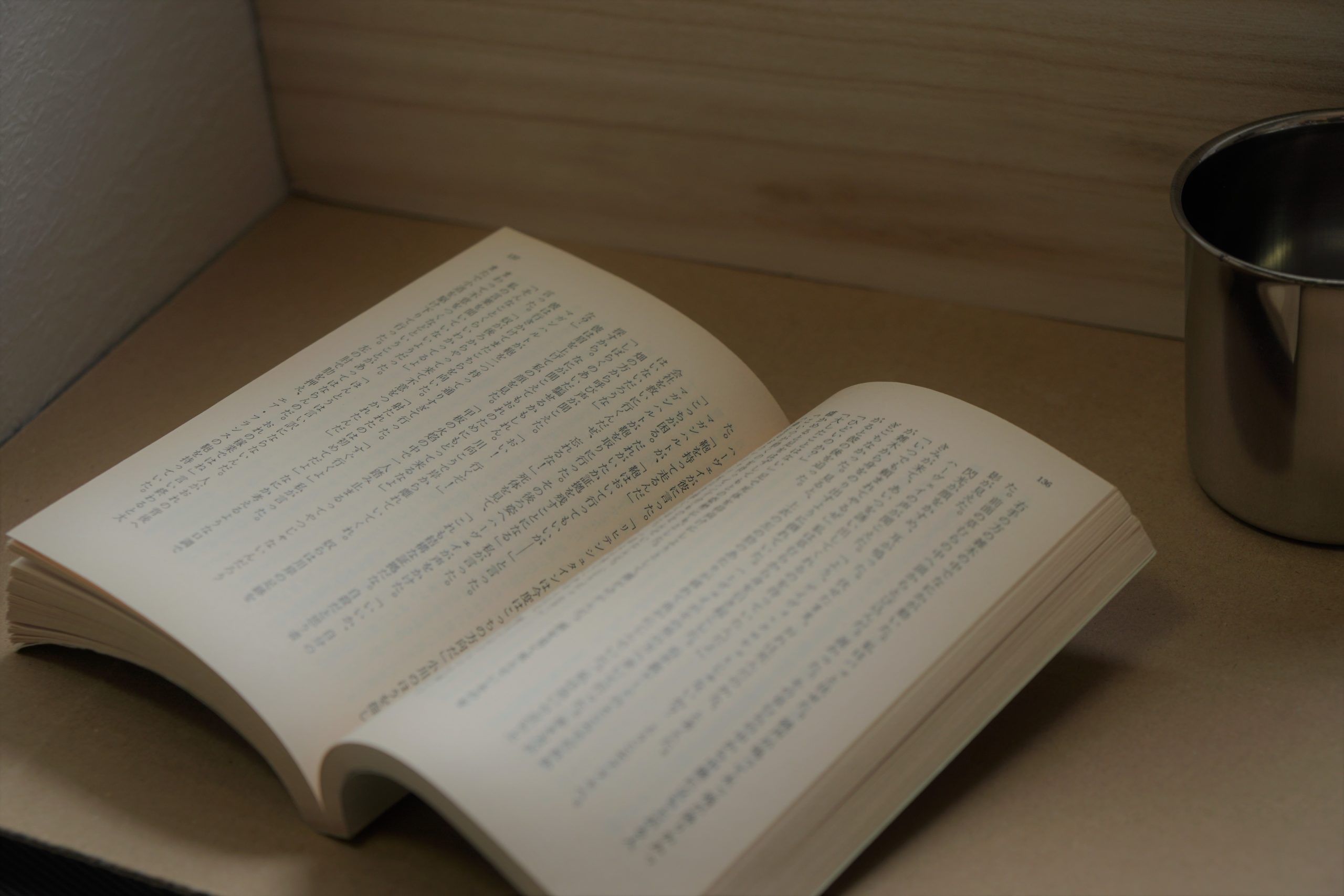
純文学とは一言で言えば「エンターテインメント性」よりも「芸術性」を重視する文学のこと。「意味は分かりにくいが、心に引っかかるものがある」「映画やアニメなどでは表現できない、文学だからこそできる表現がある」などの独自の世界観が評価される文学です。
そもそも純文学の定義とは
そもそも「純文学」という言葉が生まれたのは明治時代のこと。当時の作家・北村透谷によると、「学問のための文章でなく美的形成に重点を置いた文学作品」と定義されていました。(評論『人生に相渉るとは何の謂ぞ』より)
現代のように純文学が大衆文学と比較して語られるようになったのは、昭和時代になった頃から。当時流行し出した大衆文学と差別化するために、芸術性を重んじる作家たちが自らの文学を「純文学」を定義しました。
大衆文学との違いは「芸術性」
これだけ聞いてもやっぱり分かりづらい人には、まずは大衆文学について説明した方がイメージしやすいでしょう。大衆文学はエンターテインメント性があり、一般的に読みやすい文学を言います。起承転結がはっきりしている物語や、ミステリー小説、SF、ファンタジーなども大衆文学に分類されるケースがほとんど。
大衆文学は読者を楽しませるための、一定のルールや共通認識が存在します。起承転結がある、というのが典型的なルールです。しかし純文学にはそういったルールは存在しません。筆者が書きたいテーマについて自由な書き方をしているのが純文学の特徴です。
音楽で例えるならば、J-POPや歌謡曲が大衆文学。それ以外の前衛的・実験的な要素を詰め込んだジャンルが純文学だと言えます。
難しいイメージの純文学を楽しく読み進めるコツとは
純文学は「難しい」「つまらない」「読みにくい」とイメージされがち。実際にSNSなどでは読みやすい大衆文学に比べ、純文学は難解で読み進めるのが苦痛だという意見をよく耳にします。内容が分からず、「途中で読むのを辞めた」「挫折した」となることも。
そこでここでは、純文学を楽しく読み進めるためのコツを紹介します。筆者ももともとは純文学が苦手だったので、筆者がどうやって克服してきたか経験してきたことを踏まえて伝授いたします。
全てを理解しようとはせずに雰囲気を楽しむ
純文学作品を隅から隅まで理解しようとするのは、なかなかハードルが高い苦行。起承転結がはっきりしていないので、なぜここでそんな表現が出てくるのか、何が言いたいのか分からず悶々とさせられるケースもあります。
しかしそんな時は立ち止まらず、敢えて読み進めてみるのがコツです。すると読み終わった後に、そういえばあの部分ではこういったことが言いたかったのかと思いつくこともあります。例え思いつかなくても、読み終えたことで何かしら心に引っかかるものがあれば、それで良いのです。
書評やレビュー、著者のインタビューを読んでいろんな捉え方があると知る
とはいえ、やはり最後まで何が言いたいのか分からないとモヤモヤした気持ちが残りスッキリしませんね。そこでよく筆者がやっていたのが、小説を読んだ後に、書評やレビュー、著書インタビューを一通り読むというものでした。
人気作家の純文学作品の書評は、文芸誌や新聞の書評欄に記載され、ネットで読めるものもあります。また最近はSNSで感想を投稿している方も多いので、「そういう捉え方があったのか」「なるほど、あの書き方はそういったことを意図していたのか」と参考になる意見が見つかるはずです。
純文学は「芸術性」を重視する文学。よってその部分をどう受け手が捉えるか、感じるか、というのが、作品を知る上での重要な要素となります。筆者もこの方法で作品の「奥行き」を感じることができます。こうして小説を立体的に浮かび上げることこそが、純文学を楽しむ醍醐味なんじゃないかと感じています。
純文学の歴史を紐解いてみる
明治時代に始まった近代文学の流れから、純文学の歴史を振り返ってみましょう。
明治時代:自然主義文学から私小説へ
先述した通り、この頃は今のような純文学というジャンルがまだ確立していなかった時期です。よってどこを純文学の起源とするのは諸説あり難しいですが、近代文学の始まりとするならば二葉亭四迷が書いた『浮雲』が挙げられます。
明治時代後期には、人間が生来持っている本質的な部分を掘り下げて書かれた自然主義文学が脚光を浴びます。代表的な作品は島崎藤村の『破戒』で、1905年に発表されました。部落出身である自分の出自を隠して、小学校教員として勤める主人公の苦悩を描いた作品です。
島崎と同じく自然主義文学の代表的な作家として活躍したのが、田山花袋。1907年に発表した『蒲団』は、自身の不貞を赤裸々に描いた作品で、センセーショナルな話題に賛否両論でした。このように自身のことを綴った私小説が今後の純文学の潮流となっていきます。
【代表的な純文学作品】
『浮雲』著:二葉亭四迷
『破戒』著:島崎藤村
『蒲団』著:田山花袋
明治時代末期〜大正時代:白樺派などの反自然主義の作家たちが台頭
自然主義文学は人間の負の部分を捉えたものが多く、自己否定する作品が中心でした。それに反発して生まれたのが、人間肯定や個人主義を謳った白樺派です。同人誌「白樺」にて作品を発表し、主な人物に武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎らがいます。
また同じく反自然主義の流れで登場したのが、夏目漱石(余裕派)や森鴎外(高踏派)です。さらには永井荷風や谷崎潤一郎らによる耽美派、芥川龍之介らによる新現実主義も台頭しました。
【代表的な作品】
『友情』著:武者小路実篤
『鼻』著:芥川龍之介
『こゝろ』著:夏目漱石
昭和時代戦前:新感覚派とプロレタリア文学の隆盛と芥川賞の設立
昭和初期には、川端康成、横光利一らによる新感覚派が登場。同人誌『文藝時代』を母体として活躍しました。新感覚派は擬人法を積極的に採用したり、当時流行し出した映画の影響を受けたりといった作風が特徴です。
また同時に生まれたのがプロレタリア文学。労働者の厳しい現実について書かれた文学のことで、小林多喜二『蟹工船』などが有名です。
1935年には菊池寛が芥川賞を創設。純文学の新人賞としてその後、純文学の発展に大きな影響を与えていく賞となります。第一回の選考委員には川端康成や佐藤春夫ら。第一回の受賞作は石川達三「蒼氓」でしたが、太宰治の作品も候補になっていました。
【代表的な作品】
『雪国』著:川端康成
『蟹工船』著:小林多喜二
『檸檬』著:梶井基次郎
昭和時代戦後:無頼派の作家の活躍と、高まる芥川賞の話題性
第二次戦争直後は坂口安吾、太宰治、織田作之助などを中心とした無頼派の作家たちが人気を博しました。さらに高度経済成長期になると、三島由紀夫、安部公房、大江健三郎などが活躍しました。
石原慎太郎の芥川賞受賞作『太陽の季節』は、無秩序な行動をとる若者を「太陽族」と呼ぶ現象が起こるなど、社会現象に。この頃から芥川賞が話題になり、その後も柴田翔 の『されどわれらが日々──』や村上龍の『限りなく透明に近いブルー』などがベストセラーになりました。
【代表的な作品】
『斜陽』著:太宰治
『壁』著:安部公房
『万延元年のフットボール』著:大江健三郎
平成以降:純文学と大衆文学の境界が曖昧に
昭和より活躍していた村上龍と村上春樹のW村上がヒット作を連発。純文学の商品化が進み、音楽界の「J-POP」に倣い「J文学」という名称が売り出されたこともありました。
2004年の第130回芥川賞では、19歳の綿矢りさ(最年少受賞)と20歳の金原ひとみがW受賞し、社会的ニュースに。2008年にデビューした『日蝕』で芥川賞受賞した平野啓一郎など、若い作家が注目されました。
芥川賞作家の吉田修一がミステリー的手法を盛り込んだ小説を発表したり、同じく芥川賞作家の小川洋子が本屋大賞に選出されたりするなど、近年は純文学と大衆文学の垣根が曖昧になっています。
【代表的な作品】
『半島を出よ』著:村上龍
『蹴りたい背中』著:綿矢りさ
『火花』著:又吉直樹
おすすめの純文学作品11選
最後におすすめの純文学作品を紹介します。近代文学の名作から最近の話題作まで。この11作を読めば、純文学が何たるかがよく分かると思います。どれも比較的読みやすい作品ばかりです。気になる小説があれば、ぜひ手にとってみてください。
宇佐見りん『推し、燃ゆ』
| 発表年 | 2020年 |
| 出版社 | 河出書房新社 |
| 一言ポイント | 現代に生きるオタクの心情を正確に捉えた一作 |
第164回芥川賞受賞作。タイトルにある「推し」とは、アイドルオタクが熱狂的に支持している存在を差します。本作は推しが不祥事で炎上したのをきっかけに、主人公の高校生も翻弄される話。「推しは私の背骨だ」と表現する主人公の揺れる心情に注目です。
川上未映子『夏物語』
| 発表年 | 2019年 |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 一言ポイント | 40カ国以上で翻訳された、生命の意味を問う力作 |
パートナーなしで出産を望む主人公が、精子提供で生まれた男性と出会い…。生きるとは?生命の意味を問う一作。大阪弁の会話のやりとりはテンポがよく、読みやすい小説です。各国で翻訳され、ニューヨーク・タイムズ「今年読むべき100冊」に選ばれるなど、海外でも高い評価を受けています。
長嶋有『夕子ちゃんの近道』
| 発表年 | 2006年 |
| 出版社 | 講談社 |
| 一言ポイント | 大江健三郎賞受賞!ユーモア溢れる描写が素敵 |
アンティークショップで働き出した青年と、その周囲の変わった人たちの交わりを描いた小説。作家の大江健三郎が優れた作品を世界に知らしめようとして創設された文学賞の第一回受賞作です。長嶋有の作品は日常を独自の視点で切り取ったユーモア溢れる描写が特徴で、今作にもそれがよく表れています。
綿矢りさ『蹴りたい背中』
| 発表年 | 2003年 |
| 出版社 | 河出書房新社 |
| 一言ポイント | 芥川賞最年少受賞作品!瑞々しい感性に注目 |
芥川賞を最年少で受賞した綿矢りささんの小説。クラスで余り者扱いされた高校生のハツと、同じ境遇にいるにな川とのやりとりを描いた作品です。狭い世界で生きる高校生たちの心情が瑞々しい感性で表現された小説。当時の芥川賞選評やレビューと合わせて読むと、作品の意義をより深く知れるでしょう。
◯「蹴りたい背中」のあらすじについてはこちらの記事もチェック↓↓
3分で分かる『蹴りたい背中』のあらすじ&ネタバレ解説まとめ
村上龍『限りなく透明に近いブルー』
| 発表年 | 1976年 |
| 出版社 | 講談社 |
| 一言ポイント | 退廃的な日々を送る若者の姿に惹きこまれる! |
米軍基地のある街・福生にて、ドラッグにセックスに暴力に溺れる若者たちの青春を描いた小説。鮮烈な描写の中で、希望を見つけていく若者たちの姿に惹きこまれます。現在は経済番組の司会を務めるなど、マルチな活躍ぶりを見せる著者のデビュー作にして芥川賞受賞作。
中上健次『岬』
| 発表年 | 1976年 |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 一言ポイント | 多くの現代作家たちが影響を受けた作家の代表作 |
宇佐見りんなど現代作家たちが影響を受けた作家として名前が挙がりやすいのが中上健次。その代表作が『岬』で、続編として発表された『枯木灘』と『地の果て 至上の時』も高い評価を受けています。自身の郷里である紀州を舞台に、血縁のしがらみに翻弄される青年の苦悩と生き様を描いた傑作です。
安部公房『砂の女』
| 発表年 | 1962年 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 一言ポイント | 男が紛れ込んだ砂穴は不条理な世界の比喩か? |
男が砂穴に紛れ込み、そこから脱出を試みるが…。読んでいくうちにまるで自分も砂に囚われたかのような読者体験ができる小説。砂穴は当時の社会の比喩となっているが、閉塞した世界の書き方や、物語の展開が秀逸で読み応えがあります。
大庭みな子『三匹の蟹』
| 発表年 | 1968年 |
| 出版社 | 講談社 |
| 一言ポイント | 現代に生きる若者の心情を正確に捉えた一作 |
戦後の女流作家を代表する一人。アメリカでの生活に寂しさや孤独を感じている一人の主婦が、ある男と出会い…。会話の巧みさが見事で、現代生活の虚しさがよく表現されています。リービ英雄氏による解説と併せて読むことで、この小説の魅力がより伝わるでしょう。
太宰治『人間失格』
| 発表年 | 1948年 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 一言ポイント | 本当の自分を曝け出せない男の苦悩を描いた力作 |
太宰治の代表的作品。誰にも本当の自分を晒し出せずに苦悩する様を描いた力作です。入水自殺をする太宰の遺書と言われることもありますが、緻密な文章でしっかり構成された小説として文学史に残る作品となりました。累計発行部数は新潮文庫だけでも670万部を超えており、いまだに愛され続ける小説です。
梶井基次郎『檸檬』
| 発表年 | 1925年 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 一言ポイント | 詩的なセンスが輝く教科書頻出の小説 |
国語の教科書にも載るくらい有名な作品です。憂鬱な気分を抱えている主人公が街をうろついていた際に、ふと見つけた檸檬。それを手にとった後に主人公がとった意外な行動に注目です。読み手に判断を委ねる、鮮烈な描写や物語の展開に、これまで多くの文学的議論がなされています。
夏目漱石『こゝろ』
| 発表年 | 1914年 |
| 出版社 | 角川文庫 |
| 一言ポイント | 純文学だけでなく近代文学を代表する一冊 |
純文学だけでなく近代文学を語る上で欠かせない一作。「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」の三章から成ります。先生から私の元に届いた遺書に書かれていた先生の過去の告白とは?文庫本の最後には簡単なあらすじも書かれているので、併せて読むとよく理解できます。
おすすめの純文学作品を無料で読む紹介を公開!
今回紹介した純文学作品の多くは、Amazonが展開するサービス・Audibleにて配信されています。Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが本を朗読したものをいつでも聴けるサービス。月額1500円のサービスですが、現在、30日間無料で体験できるキャンペーンを実施中です。
読書が苦手な人でも気軽に楽しめるのも魅力。無料期間のうちに解約すれば、一切お金はかかりません。ぜひ、チェックしておきましょう!
【Audibleにて無料配信中の主な純文学作品】
・『コンビニ人間』(著:村田沙耶香)
・『火花』(著:又吉直樹)
・『こころ』(著:夏目漱石)
・『雪国』(著:川端康成)
↓↓オーディブル30日間無料登録は以下をクリック!!↓↓
今すぐオーディブルを30日間無料体験してみる!
芥川賞だけじゃない!純文学に与えられる文学賞まとめ
最後に純文学に与えられる賞をまとめました。
◯主な新人賞(公募していない)
| 賞の名称 | 開催時期 | 主催 |
| 芥川賞 | 1月、7月(年2回) | 文芸春秋社 |
| 三島賞 | 5月 | 新潮社 |
| 野間文芸新人賞 | 11月 | 講談社 |
【芥川賞(芥川龍之介賞)】
純文学の新人作家に与えられる賞の中では、知名度が最も高く社会的現象になるケースも多い。候補作は主要文芸誌(「文學界」「新潮」「群像」「すばる」「文藝」)から主に選ばれる。
【三島賞(三島由紀夫賞)】
芥川賞受賞作は候補にならず、芥川賞より前衛的な作品が受賞傾向にある。候補作は文芸誌他、単行本化した作品も対象になる。
【野間文芸新人賞】
芥川賞受賞作は候補にならない。三島賞と同様、文芸誌掲載作以外に単行本化した作品も対象になる。
◯公募による主な新人賞
| 賞の名称 | 締切時期 | 主催 | 主な受賞者 |
| 文學界新人賞 | 9月末 | 文藝春秋社 | 石原慎太郎
吉田修一 |
| 新潮新人賞 | 3月末 | 新潮社 | 中村文則
田中慎弥 |
| 群像新人賞 | 10月中旬 | 講談社 | 村上龍
村上春樹 |
| 文藝賞 | 3月末 | 河出書房新社 | 山田詠美
綿矢りさ |
| すばる文学賞 | 3月末 | 集英社 | 辻仁成
金原ひとみ |
※締切時期は年によって変わることがあります。公式ホームページでご確認ください。
◯その他の純文学における文学賞
| 賞の名称 | 対象 | 主催 |
| 谷崎潤一郎賞 | ベテラン・中堅作家 | 中央公論社 |
| 野間文芸賞 | ベテラン・中堅作家 | 講談社 |
| 川端康成文学賞 | キャリア問わず | 川端康成記念会 |
まとめ:純文学の世界に浸ろう!

いかがでしたか?純文学はとっつきにくそうというイメージが少しでも変わり、読んでみようかなと思たら幸いです。まずは今回紹介した11作品の中から、興味がある本を手にとってみてください。
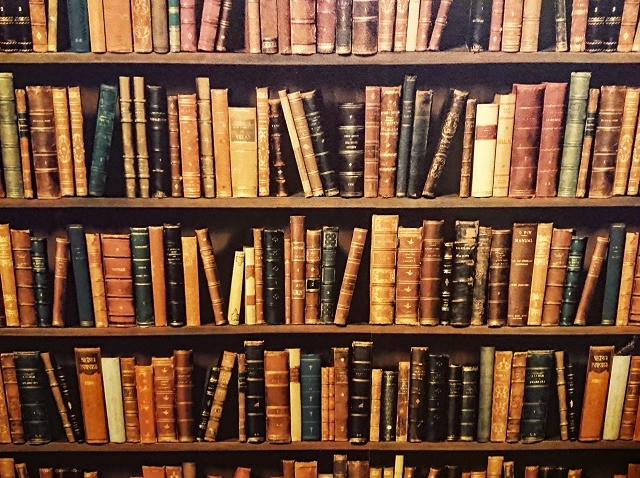
































コメント
[…] […]